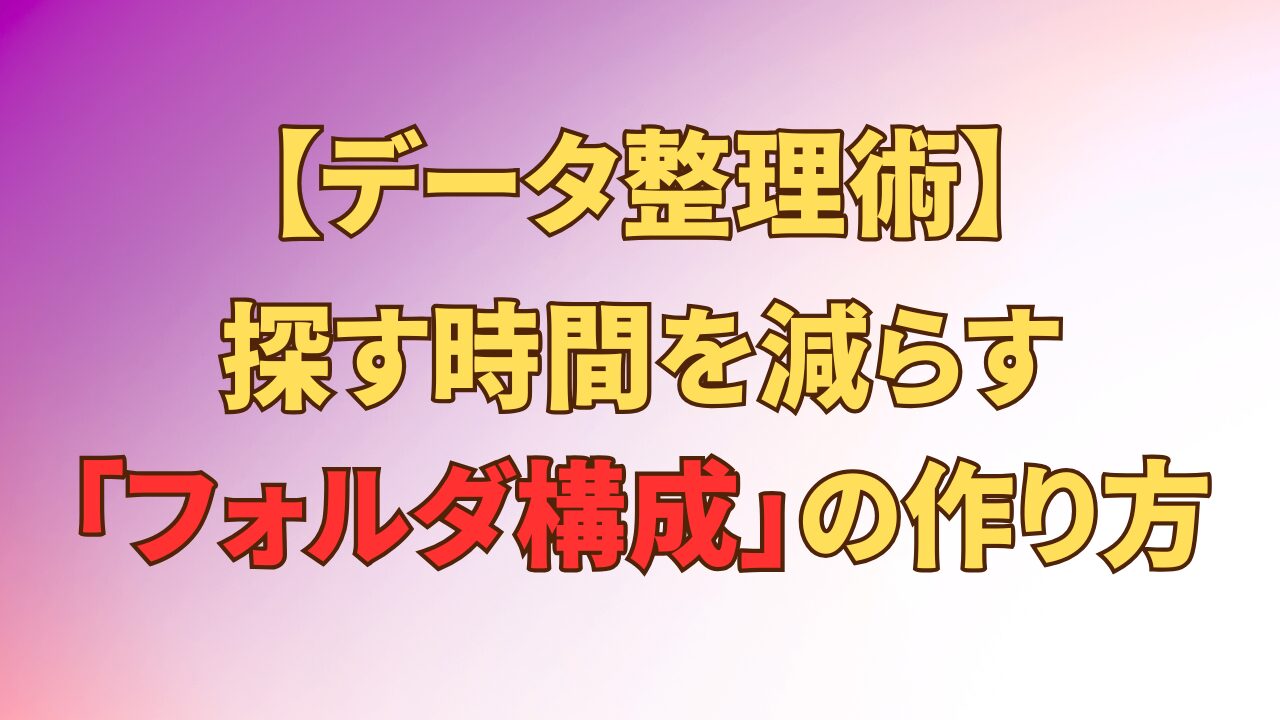パソコン内のフォルダやファイルといったデータは、何も考えずに使っていると、すぐカオス状態になります。
「ものを探す」という無駄を減らすために、フォルダ構成を見直しましょう!
本記事ではデータ整理術を、ストレージの確保やフォルダ構成案の出し方といった準備段階から、構成見直し後の運用まで解説します。
自分だけでなく、メンバーも使いやすい作業環境を作りましょう。
パソコンデータのデータ整理は「探す手間」の軽減に必須
何も考えずに使っていると、すぐにカオス状態になるフォルダやファイル。
こうしたパソコンのデータは、フォルダ構成を見直して整理することで、データを探す手間を軽減できます。
データ整理は、運用ルールを周知し、メンバーが使いやすい状態を維持することが必要です。
本記事では、具体的なデータ整理手順と、整理後の運用方法についてお伝えします。
【準備編①】データの保管場所を決める
メンバー間でデータを共用できるストレージが無い場合、まずはストレージの準備から行います。
※既にデータ共用できる状態の場合は、【準備編②】へ進んでください。
データ共用のストレージを用意できない場合は、外部ツールを利用する方法もあります。
例えばNTT東日本が運営する「コワークストレージ」は、Windowsのエクスプローラーと似たような操作感で使いやすいです。
【準備編②】フォルダの構成を決める
業務内容を洗い出し、各業務をカテゴリ分けします。
すでに存在するフォルダやファイルから、カテゴリを考えても良いでしょう。
総務の場合、以下のようなカテゴリが考えられます。
- 経理・財務
- 人事・労務
- 法務・契約書
- 補助金・各種認定
- 庶務・備品管理
- 議事録
カテゴリは、多くても3階層までにするのが理想です。
「経理・財務」であれば、以下のような階層が考えられます。
- 1階層目 大カテゴリ 「経理・財務」
- 2階層目 中カテゴリ 「発行請求書」「受領請求書」「売上集計」など
- 3階層目 小カテゴリ 「年月(2025.08)」「期(2025年度)」など
個人用フォルダ、不要データの仮置き場も設置する
業務用フォルダとは別に、「個人用フォルダ」「不要データの仮置き場(ゴミ箱)」も設置しましょう。
個人用フォルダには、「個人で使っているが、メンバー間で共用していないデータ」を入れられるようにします。
- 1階層目 大カテゴリ 「個人用」
- 2階層目 中カテゴリ 「佐藤」「鈴木」などメンバー名
- 3階層目 小カテゴリ 各メンバーで自由に管理
また、不要データの仮置き場として「ゴミ箱」フォルダも置くと便利です。
不要データは「ゴミ箱」フォルダに移動し、年1回や半年ごとなど時期を決めて削除します。
削除はメンバーや上司の承認を得てから実施することで、実は必要だったデータを誤削除する可能性を減らすことができます。
「その他」フォルダは作成しない
カテゴリ分けの注意点として、「その他」フォルダは作らないようにしましょう。
迷ったら何でもここに入れてしまう恐れがあるためです。
カテゴリを仮作成できたら、メンバーと協議しながら調整する
必要なカテゴリが洗い出せたら、Excelなどでフォルダ構成を仮作成します。
仮作成したフォルダ構成をメンバーに見せ、協議しながら使いやすい構成に調整しましょう。
【整理編①】フォルダ構成を反映する
フォルダ構成が決まったら、データ整理開始です。
構成通りに、ストレージへフォルダを作成していきます。
新規フォルダ作成には、「Ctrl + Shift + N」のショートカットを使うと便利です。
フォルダは階層ごとに「01_」から始まる番号で順番を調整しましょう。
- 01_経理・財務
- 02_人事・労務
- 03_法務・契約書 など
個人用フォルダは「98_個人用」、不要データの仮置き場は「99_ゴミ箱」と設定することで、後から追加したい業務カテゴリが増えても、最低限の順番調整で済みます。
【整理編②】ファイルを該当フォルダに移動させる
既存ファイルを、業務カテゴリに該当するフォルダへ移動させます。
ファイルの移動ができたら、ファイル名の整理も行いましょう。
例えば請求書や領収書は、「【請求書】日付_顧客名_金額」といったファイル命名ルールを決めて名前を統一します。
ファイルをコピーして最新版を作成している場合は、バージョン管理が必要です。
ファイル名の冒頭か末尾に、日付8桁(「20250805」など)を記載することで管理しましょう。「最新」とつけるのはNGです。
【運用編】整理された状態を維持するために注意すること
せっかく整理したフォルダ・ファイルも、油断するともとのカオス状態に戻りがちです。
運用時の注意として、整理整頓された状態を維持するための方法を紹介します。
年度が変わったら、前期のデータはフォルダにまとめる
各カテゴリに保存されるデータは、当期・前期・前々期の3年度分が見えていれば十分です。前々期よりも過去の年度は、「_過去期」フォルダを作成して移動させます。
年度ごとにまとまっていれば、保管期限を過ぎたデータを削除するときにも便利です。
前期のデータをまとめるついでに、不適切な場所に保存されているデータが無いかチェックしましょう。
不要データの削除ルールを決める
不要データを「ゴミ箱」フォルダに入れた後の削除ルールを決めると、いつまでもデータが残っている状態を防ぐことができます。
メンバー内では削除の可否を判断できない場合もあるため、上司や経営陣と相談して「最後の更新から2年以上経ったデータは削除」などと決めるのがベターです。
定期的に不要データを整理することで、ストレージの圧迫も防げます。
複数箇所にデータを置く場合はショートカットを使う
例えば、ある企業との契約書を会議で提示するため、「法務・契約書」フォルダ内のデータを「議事録」フォルダにも置いておきたいケースなどが考えられます。
このとき、「議事録」フォルダに「法務・契約書」にあったデータをコピーすると、会議の場で修正した内容を「法務・契約書」フォルダのデータにも反映させる手間が発生します。最悪、コピー元の方を最新版にし忘れて「どちらが正確なデータかわからない状態」になってしまう可能性もあります。
複数箇所にデータを置く場合は、コピーせず、ショートカットを使いましょう。
ファイルを右クリックし、メニュー一覧から「ショートカットの作成」を選択することでショートカットが作成できます。
ショートカットを使うことで、複数箇所にあるデータを差し替える作業が省けます。
まとめ:データ整理で「探す手間」を減らそう!
パソコンのデータ整理手順のまとめです。
■準備編
・データ保管場所となる共有ストレージの確保
・フォルダ構成の決定
■整理編
・決定した構成通りにフォルダを作成
・データを移動し、ファイル名を統一
■運用編
・年度が変わったら過去年度のデータを移動
・不要データの削除ルールを決める
・データは複数コピーせずショートカットを使う
「ものを探すこと」は、何も生み出さないただの時間泥棒です。
必要なデータへすぐにアクセスできる環境を作ることで、無駄な時間を減らしましょう。
フォルダ構成は一度整理したら終わりではなく、定期的に見直すことが大切です。
ぜひ、この機会にデータ整理に挑戦してみてください!